関東地協医学生のつどい in 栃木 1日目
―大谷フィールドワークと関口医師講演「SDHと社会的処方」―

日時:2025年11月8日(土)
場所:宇都宮市大谷地区・医療生協本部
主催:民医連関東地協 医学生のつどい(KIT)
参加:医学生・医師・職員 約30名
講師・案内:関口真紀 医師(宇都宮協立診療所)
目次
- 関東地協医学生のつどい in 栃木 開催
- 大谷フィールドワーク ― 石のまちの歴史を歩く
- 石を掘る人びとの健康と暮らし
- 平和観音に込められた祈り
- 関口医師講演「SDHと社会的処方」
- 医学生の声 ― 学びを自分の原点に
関東地協医学生のつどい in 栃木 開催
2025年11月8〜9日、関東地協医学生のつどい(KIT)が栃木で開催されました。
テーマは「地域医療を知り、SDHを学ぶ」
1日目は宇都宮市大谷地区・大谷資料館でのフィールドワークと関口医師による学習講演、
2日目は地域の居場所づくり「カムカム★カフェ」と武井医師の学習講演へと続きました。
関東各地から集まった約30名の医学生・医師・職員が参加し、
地域の歴史・社会・医療を結びつけて学ぶ1日となりました。
大谷フィールドワーク ― 石のまちの歴史を歩く

参加者はバスで「石のまち」宇都宮市大谷地区へ向かいました。
案内を務めた関口医師は、車中で地域の成り立ちを紹介しました。
「大谷石は、火山灰が海の底で堆積してできた軽く柔らかな石。
建築材として全国に広まり、地域の暮らしを支えました。」
車窓からは、石蔵や採掘場跡が見え、かつての繁栄を物語ります。
採掘は農家の副業として始まり、冬場には次男・三男や女性も坑内で働きました。
1本150キロを超える石を肩で担ぎ上げる重労働。
関口医師は「女性が坑内に入ることが禁じられても、人手不足で隠れて働くこともあった」と語りました。
地域の発展の陰に、過酷な労働があったことを学生たちは知りました。
石を掘る人びとの健康と暮らし
採掘現場では、粉塵によるじん肺や腰・膝の障害が多発しました。
「電動ノコギリの導入後は粉塵が増え、呼吸困難に苦しむ人が多くいた。
夫を亡くした女性たちが多く暮らす“未亡人地区”と呼ばれる地域もあった」と関口医師。
学生たちは、健康の背景に社会構造があることを実感しました。
平和観音に込められた祈り

戦没者慰霊のために掘られた「大谷平和観音」を訪れました。
地元の方が自らノミを手に掘り始め、のちに東京芸術大学の飛田朝次朗教授の協力で完成した高さ27メートルの観音像です。
関口医師は、「この観音像には、亡くなった人だけでなく、生き残った人びとの祈りが込められている」と語り、参加者全員で静かに黙祷を捧げました。
関口医師講演「SDHと社会的処方」

後半は医療生協本部にて、関口医師による学習講演「SDHと社会的処方」が行われました。
大谷FWでの学びを受けて、医療と社会をどう結びつけるかをテーマに講義が進みました。
関口医師は問いかけます。
「なぜ同じ病気でも、発症する人としない人がいるのか?
遺伝や体質だけではなく、貧困、教育、雇用、住環境、人とのつながり――
社会の条件が健康を決めている。それがSDHです。」
さらに「社会的処方」という考えを紹介。
「薬や検査だけでなく、人と人とのつながりを“処方”することが医療に求められている。
診察室の外にある“居場所”こそが、患者を支える医療の一部です」と語りました。

宇都宮協立診療所や生協ふたば診療所で行われている「カムカム★カフェ」「まちの保健室」などの実践も紹介され、医療と地域の協働による“社会的処方”の姿が描かれました。
医学生の声 ― 学びを自分の原点に
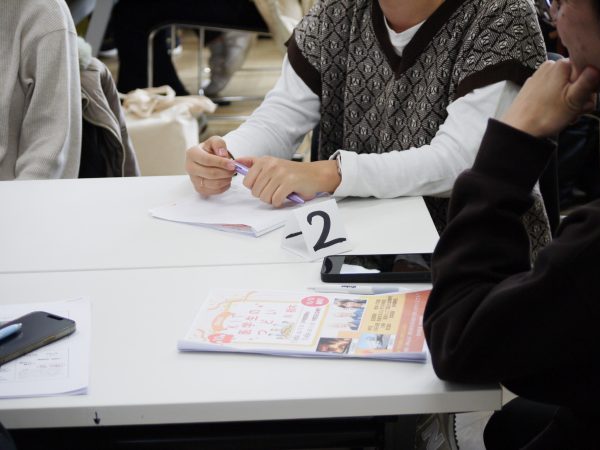
講演後のグループワークでは、医学生たちが1日の学びを共有しました。
「観光で訪れたことのある大谷が、労働と健康の歴史をもつ場所だと知り衝撃を受けた。
地域の背景を知ることで、医療の意味が変わった気がした。」(栃木・医学生)「身近な地域の産業と健康を結びつけて学べた。
社会的要因を意識する医療の大切さを実感した。」(千葉・医師)「SDHの視点で医療を考えることは、患者さんを“ひとりの生活者”として理解することだとわかった。」(神奈川・医学生)
「民医連の“また来てね”という姿勢に、人を切り捨てない医療の哲学を感じた。」(神奈川・医学生)
学生たちは、「病気の背後にある社会構造を見つめる医療」を自分の原点として持ち帰り、
翌日の学習へとつなげました。
(栃木民医連 事務局)
