軽部憲彦医師が語る「私と民医連」
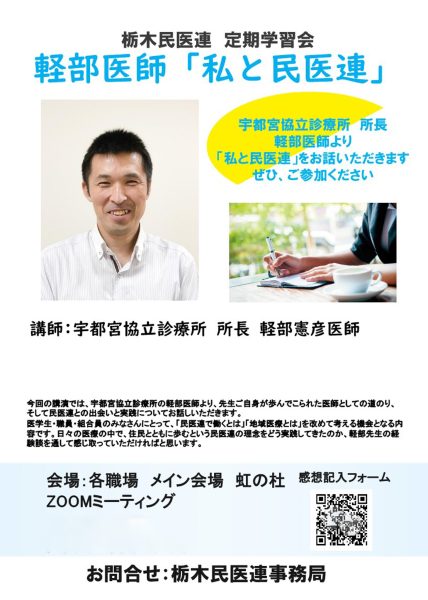
開催概要
2025年10月29日(水)14:00〜16:00、栃木民医連は定期学習会を開催しました。
講師は宇都宮協立診療所 所長の軽部憲彦医師。テーマは「私と民医連」。
約6年ぶりの講演となり、多くの職員が会場とオンラインで参加しました。

民医連との出会いと医師としての歩み
軽部医師が民医連に入職したのは1997年4月。以来28年にわたり、地域に根ざした医療を実践してきました。
学生時代、偶然届いた「宇都宮協立診療所からの実習案内のはがき」が、民医連との最初の出会いでした。実習を通じて「病気は生活や社会と深くつながっている」という気づきを得たことが、地域医療への関心を深めるきっかけとなりました。
当時、地域医療を「へき地で行う医療」と漠然と考えていた軽部医師。しかし、関口医師からの「この地域もまた地域医療なんだよ」という言葉が胸に残り、地域で暮らす人々の医療に真剣に向き合う決意を固めました。
群馬民医連での研修と学び
初期研修は群馬民医連で行われました。前橋協立病院や利根中央病院などを回りながら、幅広い症例と多職種連携を経験しました。
特に印象的だったのは、研修医会や青年医師の会の存在です。職種や所属を超えて自由に意見を交わし合う場があり、「仲間と共に成長する文化」が根づいていたといいます。
また、群馬民医連独自の人権・平和フィールドワークを通して、軽部医師はハンセン病問題や戦争体験に触れ、「医療は人権と深く結びついている」ことを学びました。
草津の国立療養所「栗生楽泉園」で出会った元患者さんの話から、「医療者として歴史の中の差別や痛みに学ぶ姿勢」を心に刻んだと語りました。
宇都宮での地域医療と在宅ケア
研修後、宇都宮協立診療所に戻り、地域医療に本格的に携わるようになります。
診療所の小規模な現場だからこそ、患者・家族・職員が「家族のように」関わり合い、生活に寄り添う医療を実感したといいます。
特に訪問診療の現場では、患者や家族の生活そのものを支えるケアの重要性を感じたと述べました。
在宅での看取りの経験を通して、「人が最期まで自分らしく生きることを支える医療の尊さ」を学んだと振り返りました。
また、糖尿病診療にも長年携わり、立川相互病院や多摩南クリニックでの研修を通じて「生活と病の関係性」を深く学びました。糖尿病患者の心理的負担に向き合う中で、「病気を治すだけでなく、心を支える医療」の大切さを痛感したと語りました。
民医連綱領から学ぶ医療の原点
後半では、軽部医師が改めて「民医連綱領」を読み直し、その理念を自らの実践と重ねて語りました。

「民医連は、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織であり、地域とともに歩む医療を実践することが使命です。」
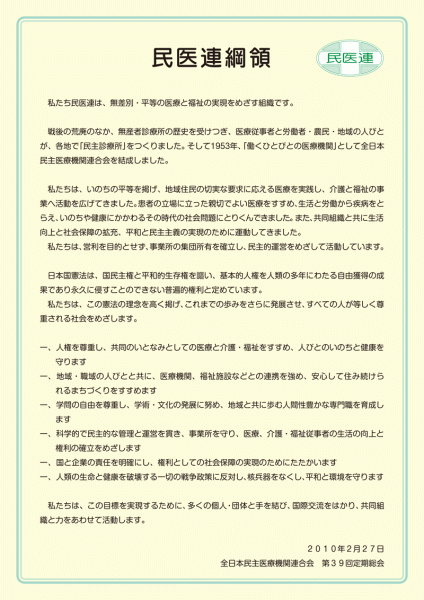
民医連綱領に記された六つの柱――人権の尊重、地域との協同、学問の自由と専門職の育成、民主的運営、社会保障の充実、そして平和の実現――について、軽部医師はそれぞれを具体的に解説しました。「私たちが出会う患者さん一人ひとりの暮らしの中にこそ、人権や社会の不平等の問題が見える」と語りました。
また、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」にも触れ、「現場から声を上げ、社会を変えていくことが医療者の責任である」と訴えました。
おわりに―地域とともに歩む医療へ
講演の最後に軽部医師は、28年の民医連での歩みを振り返りながら次のように語りました。
「民医連の医療は、諦めず、困難な人に寄り添い、みんなで協力して進む医療です。
目の前の患者さんを少しでも幸せにし、地域の人々と共に幸せになれる社会をつくっていきたい。」
静かな語り口の中にも、地域医療への熱意と民医連の理念への確信があふれた2時間。
参加者からは「自分がなぜこの職場で働くのかを改めて考えるきっかけになった」との声が多く寄せられました。
(文・写真/栃木民医連事務局)
