「民医連医療」11月号で栃木の取り組みが紹介されました
― 生協ふたば診療所・諏訪看護師長の実践と、工藤事務局長の「共通言語」への思い ―
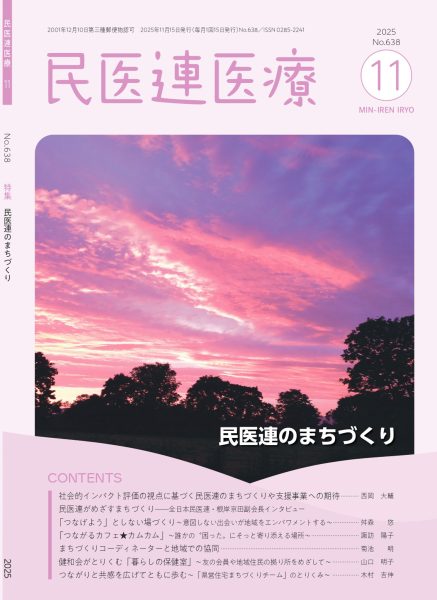
目次
全日本民医連が発行する機関誌『民医連医療』11月号(No.638)に、栃木の取り組みが紹介されました。
一つは、生協ふたば診療所の諏訪陽子看護師長による地域の居場所づくり「つながるカフェ★カムカム」。
もう一つは、愛知県立大学の久保田貢教授による寄稿「治安維持法100年と民医連」の中で、2025年4月に栃木で行われた講演について触れられています。栃木民医連事務局長・工藤鉄明が講演後、久保田教授に語った「共通言語」という言葉が紹介されています。
■ 誰かの“困った”に寄り添う ― 「つながるカフェ★カムカム」
「病気のあるなしに関係なく、子どもも大人も高齢者も、どなたでも立ち寄れる地域の居場所」。
それが、生協ふたば診療所が運営している「つながるカフェ★カムカム」です。
諏訪さんがこの活動を始めたきっかけは、外来で出会う患者さんとの関わりでした。
病気だけではなく、孤立や貧困、家庭の悩みを抱える方に出会う中で、「診療所に来なくても気軽に関われる場所があれば」と感じたことが出発点だったそうです。
2018年には、子どもたちが宿題を持って集まり、一緒にご飯を食べる「子ども企画」をスタートしました。
そして2021年、介護事業所「ふれあいコープ」と協力し、「医療・介護・福祉が連携する場」として「つながるカフェ★カムカム」を立ち上げました。
現在は「みんなの食堂」として月2回開催しており、子どもから高齢者まで、さまざまな世代が交流しています。
印象的なエピソードとして、ひきこもり状態にあった20代の女性がカムカムに参加し、ボランティアとして活躍するようになった事例が紹介されています。
「必要とされる経験を重ねることで、少しずつ社会に踏み出すことができた」と諏訪さんは語っています
カムカムは「誰かの困ったにそっと寄り添える場所」。
診療所が地域と手を取り合い、「医療を超えたつながり」をつくる実践として、全国に紹介されています。
■ 「共通言語」を育む学び ― 栃木民医連の講演から
同号では、もう一つの栃木の取り組みとして、栃木民医連が開催した講演も紹介されています。
愛知県立大学の久保田貢教授による寄稿「治安維持法100年と民医連」では、2025年4月に栃木で行われた講演について触れられています。
「これで共通言語ができた」と栃木民医連・工藤鉄明事務局長が私に語った
ここでいう「共通言語」とは、民医連綱領を理解し、実践していくための基盤となる歴史認識のことです。
戦争と医療、憲法と平和の関係を職員が共有することが大切です。
久保田教授は講演の中で、戦前の「無産者診療所」の歴史や治安維持法による弾圧を詳しく紹介し、戦後の民医連運動が「平等の医療と福祉」「反戦・平和」の理念の上に築かれていることを伝えています。
「このことを民医連内で共有し、共通の記憶を社会全体に広げたい」
■ 栃木から広がる“人と人のつながり”
ふたば診療所の「カムカム」も、工藤事務局長が語る「共通言語」も、どちらも「人と人が支え合う関係を地域に根づかせる」取り組みです。
医療の現場から生まれた温かなつながりと、歴史を学び未来へつなぐ学びの実践。
この二つの流れがいま、栃木の民医連の活動の中で確かな力となって広がっています。
(栃木民医連事務局)
