【定期学習会レポート】
小池先生と考える「ナッジ」の力
―― 自然に“行動したくなる仕組み”を、あなたの職場にも
目次

ナッジって何だろう?
7月30日に開催された定期学習会のご報告をお届けします。
この日は慶應義塾大学の小池智子先生をお迎えして、「ナッジを使った職場づくり」をテーマにお話しいただきました。
「ナッジ」って聞いたことありますか?
強制ではなく、そっと背中を押してあげるように人の行動を促す仕組みのことなんです。
医療や介護の現場、そして私たちの日常にも、実はたくさん取り入れられているんですよ。
わかっていても、できないことってあるよね
「整理整頓、大事だよね」「手洗いはちゃんとやらなきゃ」
頭ではわかっていても、忙しさや疲れから、つい後回しにしてしまうこと、ありますよね。
そんなとき、「頑張るしかない」ではなく、“頑張らなくても自然にできる仕掛け”があったら…?
それが、ナッジという考え方です。
ナッジの考え方が、現場を変える
例えば、こんな工夫があるんです。
- ドアノブの形を「押す」「引く」と迷わないようにする
- 足跡マークで、トイレの後に自然と手洗い場へ誘導する
- ゴミ箱の形や色を工夫して、分別を間違えにくくする
どれも、無理やりではなく、「気づいたらやっていた」というような行動の工夫。
先生はこうした身近な例をたくさん紹介してくれて、参加者のみなさんからは「うちの職場でもやってみたい!」と声が上がっていました。
「頑張らないでできる」がカギ

医療や介護の現場は、日々の業務でコップの水があふれそうなほどの忙しさ。
そこに「新しいことをやってください」と言われても、正直しんどい。
だからこそ、小池先生は「職員の努力や意識に頼るのではなく、仕組みで自然とできるようにしていこう」と繰り返し伝えてくださいました。
ワークショップも実施!
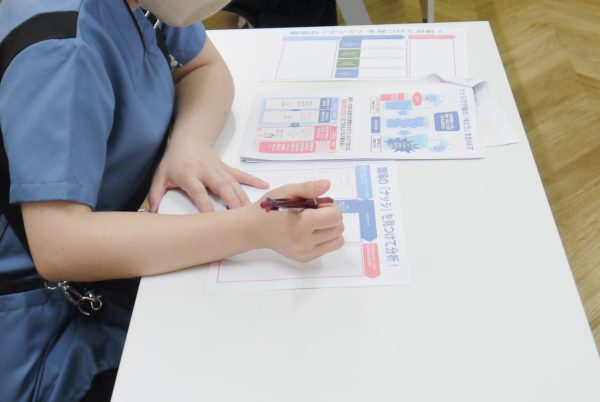
後半には、グループでのワークショップも行いました。
「自分の職場だったら、どんなナッジが使えるかな?」と考えながら、現場に根ざしたアイデアが次々に出てきました。
- 感染対策のための動線に矢印を描いてみる
- 物品配置を少し工夫して探す時間を減らす
- 職員のモチベーションが上がる“しかけ”を用意する
参加者の声
- “頑張らないでできる”って、私たちの現場には本当に必要だと感じました
- ナッジは小さな工夫だけど、すごく奥が深い!
- 自分の部署で、すぐに試してみたいアイデアがいくつもありました
小コラム:ナッジの具体例5選
- 手洗いの足跡マーク
子どもたちがトイレの後、足跡をたどるだけで自然と手洗い場へ。4%→74%に手洗い率がアップしたそうです。 - 男性トイレの的シール
的をつけると、自然とそこを“狙って”くれることで、飛び散りが減り、掃除の手間も削減。 - 最初から「参加」に設定しておく(オプトアウト)
「希望者は申し込んでください」よりも、「全員申し込んであります、辞退したい人だけ申告して」という方が、参加率が上がるんです。 - 選択肢は少ないほうがいい?
ジャムの販売実験では、24種類より6種類の方が売上増。人は選びすぎると選べなくなるそう。 - 見せ方を工夫する(フレーミング効果)
「90%助かる」と「10%助からない」は同じ内容。でも受け取り方はまったく違います。
おわりに
「行動を変えるには、意志よりも環境を変えるほうが効果的」。
この言葉が、今回の学習会で一番心に残りました。
日々の現場で、少しでもラクに、でもしっかり成果が出せるような工夫を、これからも一緒に考えていけたらと思います。
