医学生学習会「健康格差の原因を知ろう」〜SDH(健康の社会的決定要因)について学びました〜
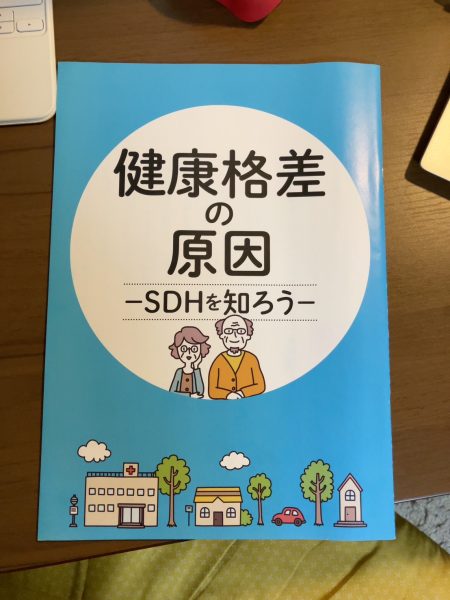
4月、栃木民医連では医学生を対象にした学習会を開催しました。テーマは「健康格差の原因を知ろう」。SDH(Social Determinants of Health:健康の社会的決定要因)について、パンフレットを用いながら学びを深めました。
今回の学習会では、単に個人の努力や生活習慣だけで健康が決まるのではなく、社会的な背景や格差が健康に大きな影響を与えていることを改めて確認することができました。医学生たちは、これまでの「病気は自己責任」という考え方に疑問を持ちながら、社会的要因を含めた広い視点で健康問題を捉えることの重要性を学びました。
学習の主な内容
- 「病気は自己責任か?」を考える
健康を自己責任論で片付けるのではなく、背景にある貧困、労働環境、教育機会の格差などに目を向ける必要性があることに気が付きました。 - SDH(健康の社会的決定要因)とは
医療だけでなく、社会環境(労働、教育、住環境、社会的支援など)が健康を左右するという考え方です。 - 社会格差と健康格差の具体例
所得や地位によって健康状態や寿命に大きな差が生じることを、データやグラフを通して理解することができました。特に、職業階層による心臓病の死亡率の違いなどが紹介されおり、その結果に驚いていました。 - タクシー運転手の健康問題を通じた理解
長時間労働や深夜労働が健康リスクに直結すること、また社会構造そのものが病気を引き起こす背景になっていることを知ることができました。
参加者の声

今回の学習で気づいたこと・発見したこと
- アメリカは一人当たりの所得が高いにも関わらず、平均寿命は他の先進国よりも低いこと、また年々短くなっていることに驚いた。
- 同じ職場でも、職の地位によって病気になる可能性やリスクに大きな差があることを実感した。
- 社会的階層で健康格差が生まれており、お金に余裕がある方が医療を受けやすいこと、また原因には10個ほどの領域があり、それを改善目標とすることが重要だと学んだ。
- 経済格差によって平均寿命に10年以上の差があることに驚いた。
全体を通しての感想
- 社会的に健康を阻害されている人は、知識や財産などの面でも苦労を強いられている。そのため、政治を行う高所得者がこの現状を理解しないことで、負の連鎖が続くのではないかと考えた。
- 健康は自己責任だけでなく、社会的要因が大きく関係していることがよくわかった。
- 医療者として、健康にどのような社会的背景が影響するかを学び続ける必要性を強く感じた。
- 他の参加者と意見交換をすることで、より多角的に社会的格差について考えることができた。
今後学びたいこと・取り組みたいこと
- SDHに関連する他の要因についてもさらに深く学びたい。
- 健康格差を生み出す10の領域をどのように克服できるかについて考え、学びたい。
- 健康格差を是正するために、医師としてどのような行動ができるかを具体的に考え、実践していきたい。
次回の学習会は5月13日に予定しています。次回は「子ども時代と健康格差」について、さらに深く学びを進めていきます。引き続き、医療者として、また一人の市民として、社会課題に目を向けながら学んでいきます。
